
ダウン症の子は成長や障害に特徴がありますよね。
そのために人とのコミュニケーションが難しい場合もあります。なので、出来るだけ子供とのふれあいを通して気持ちを理解できれば、親と子の気持ちを繋ぐツールになりますよね。
そのためにおもちゃは頼りになるものなんです。
おもちゃのカテゴリーを、いろんな目線で見れば自分の子供に最適のおもちゃが見つかるかりますよ!
私は、おもちゃを見ている時に「良いアイデアが沢山あるな」と思いました。
言語病理学などから、100種類以上のおもちゃを7種類に分類して、うまく自分の子の感覚に当てはめれば良いことが起こると思います。
また、おもちゃを選ぶだけでなく、おもちゃを通して子供と一体になりましょう。
その時に、楽しい未来を想像することがさらに大切です。
未来が楽しければ今も過去も変えてしまう力があります。それにはより楽しさをイメージ出来るほど良いです。
おもちゃは子供と大人をつなげる大切な要素なんです。
私の次男はダウン症です。
ダウン症の幼少期を通して、おもちゃは子供の気分をかえる最高のアイテムだし、それが自分を助けてくれたら良いですよね。
今回は、子供にあった最適なおもちゃを決める手順について話していきますね。
大人も一緒にもう一度おもちゃについて考えてみませんか?
目次
ダウン症の子供の特徴

ダウン症の子には特徴があります。
うまく子供の特徴を掴んで、それにあったおもちゃを気に入ってくれるとより素敵な日常になりますよね。
・言葉がきれいに発音出来ない、伝わりきらない
ダウン症の子は舌が健常者より数割長いです。
なので母音のあ行がうまく発音出来ないことが多いと言われています。
聞き取りずらいと言葉のコミュニケーションが多いと、お互いに伝わらないので、言葉と合わせて親が子供にイメージをさせることが重要です。
・聴力が弱い傾向
呼びかけに反応しないこともあります。
その場合は、おもちゃを利用して親がやりたいことを伝えてみましょう。
お風呂もトイレもおもちゃを絡めてみましょう。
・筋の張力が弱い
ダウン症の子は筋力が弱いのではなく、筋を張る張力が弱いです。
健常者の子は普通生後6ヶ月くらいで、筋の緊張状態が高まっていき、両手が独立してコントロール出来るようになるのが、ダウン症の子ではその傾向が少ないです。
なので筋の緊張を高めて遊べる玩具がよいですね。
おもちゃ7カテゴリーとは?
昔からおもちゃは、ただ大量に発売されるだけでなく、よく見ると様々な教育スキルを取り入れています。
各ブランドともそのジャンルで競争していますね。
また、カラフルで耐久性があり、子供から大人までに魅力的であることは言うまでもありません。大人でもあまりにも精巧な乗り物系やフィギアなど、おもちゃにハマる人も多いですよね。
子供が好きなおもちゃはもう少し単純で知的なものが多いです。
お気に入りのおもちゃを7つのカテゴリーに分けてみましたので子供に合ったおもちゃのヒントにしてくださいね。
【おすすめ7カテゴリー】
・無限系おもちゃ

子供は、探求を通じてすこしづつ学んでいきます。
無限系とは、反復を繰り返すおもちゃのことです。
無限系おもちゃで遊ぶようになると、子供は自分の行動がものの形を変えれることに気付き始めます。
また無限おもちゃは、手と目の協調性を高めるように設計されているので、子供のの初期のコミュニケーションと問題解決のスキルを身につける反復をさせることを覚えさせるのに良いです。
これらには、楽器やロールタワー、ボタンを押すと音がなるもの、スタッキングカップなどもあります。
反復の行動はダウン症の子供が得意とするところなのでうまく利用したいところです。
・パズル系おもちゃ
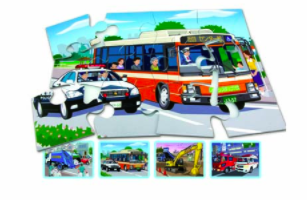
パズルは大人でも難しですが、子供向けに2ピースパズルがあります。
2ピースだけなのに結構値段が高くて躊躇してしまう親も多いはずです、、
パズルは子供に達成感を与えることが出来るし、自動車のパズルであればよりイメージを覚えさせるのに役に立ちます。
パズルは本当に最高です。
なぜなら、曖昧な言葉ではなくイメージを頭の中に残すことが出来るからです。
それも自分が組み立てたものであればより強く脳の中に残ってくれるからです。
パズルは、マッチングパズル、フロアパズル、サウンドパズル、アルファベットパズルなど色々あります。
・オープンエンド系おもちゃ


オープンエンドとは何時間でも遊べて、自由に組み立てれるおもちゃです。
これらは子供の想像力を必要とします。
オープンエンド系のおもちゃは、言語習得、社会性スキル、自己表現を高めるように設計されています。
私のお気に入りは、レゴやタイル系の組み立てもの、おままごとや迷路づくり、ブロック、ブレインフレークなどがあります。
ダウン症の子供には難易度が高いものもあります。
目標のイメージがないので、同組み立てたら良いか分からず投げ出しがちです。
そのために親が手本を見せてあげることです。それがないと1人で遊ぶのには根気がいります。
・ボードゲーム系おもちゃ

ボードゲームは、家族全員で一つのことをするのに最適です。
子供はゲームのようなルールがきまっているものに参加する時に、指示に従う、待機する、スポーツマンシップなどの理解をちいさな世界から体験することが出来ます。
一部のボードゲームはチームワークに焦点を当てているものもあり、社会的な関係を磨けます。
ダウン症の子供は、「みんなが楽しいと自分も嬉しい!」という考えの子が多いと感じるので、対戦するよりみんなで作り上げるようなゲームがおすすめです。
たとえば黒ひげ危機一発も、みんなで協力して剣をさして黒ひげを飛ばすので対象になりますね。
・感覚系おもちゃ
おもちゃの多くは感覚的な遊びを重視しています。
香りや動き、音などが含まれています。
感覚おもちゃは子供の感覚を刺激し、子供たちが自分の感覚をより発展させるような設計がされています。
ダウン症は歌が好きだし、動きも好きです。
皆で踊ることが大好きです。
香りや色、音なども色々混ぜて楽しむことで、より感性を発達させてあげたいですね。
五感を使ったイメージは脳の記憶に残りやすいのでおすすめです。
これらには、水風船、ディスカバリーパテ、ポップチューブ、ピンアートなどがあります。
・小手先系おもちゃ

細かな運動は、より小さな動きを必要です。
小手先系おもちゃは、子供が指や手首などの小さな筋肉を動きを覚えるのに役に立ちます。
本格的なおもちゃでなくても良いです。
たとえば、ピンセットやスポイト、ステッカーでも十分に楽しめます。
ダウン症の子は指が太いため小さいコントロールが難しいかもしれません。ただ、アートの分野で活躍している方も多いので、そういう人達は好きにさせるきっかけがあったりするはずです。
いきなり出来るようになったりはせず、きっかけがあったり、継続が必要です。
おもちゃを通してその時がくるまでに、下地を作っておいてあげるのもいいですね。
そんな未来を想像しながら遊ぶと、可能性が高まります。
私のおすすめおもちゃ
7つのカテゴリーに分けて、その特徴をお伝えしました。
私がおすすめなのは、「パズル系おもちゃ」と「感覚系おもちゃ」です。
なぜなら、この2つのおもちゃは、子供のなかにイメージを作りやすいからです。
イメージが出来ると何が良いかというと、記憶に残るのに有利だからです。
記憶に残っていれば、その記憶を使ってもっと良い未来につなげる事が出来ます。
その方法は、楽しい記憶を組み合わせもっと、今まで見たこともないようなおもちゃを想像できます。
それは、子供一人ではできません、親の強力が必要なのですね。
子供と一緒になって「もっと楽しい」を作ることで、そこから子供は沢山学んでいきます。
子供の頃、自分で新しい遊びを作りませんでしたか?男の子であれば、新しい遊び場=秘密基地のようなものです。私は、子供の頃、近くの山に友だちといって、洞穴をつくって1日中遊んでいましたし、それは似ごとに巨大化したし、今でもワクワクしている感覚が残っています。
つまりイメージがどんどん組み合わせたり、くっつけたりして新しいことを想像することは精神的な成長に繋がるのですね。
親が子供目線に合わしてあげる
世の中に沢山おもちゃがありますが、子供任せに遊ばせては効果半減です。
なぜなら、子供の遊んでいる時の気持ちを知ることが親にとって重要なことだからです。
多くの親は、自由におもちゃで遊んでくれてればいいと考えます。
しかし、自分も一緒に遊ぶことで、親も一緒に子供の世界、つまり子供の臨場感を知ることが出来ます。この臨場感を共有することが子供から大きな信頼を得るポイントなんです。
そうすれば、微妙な心情の変化に気づいて、声をかけるタイミングなどを工夫できます。
すると子供はより遊びに集中できたり、ママが見てくれてる安心感を得て、より自由にいろんな遊びに興味をもってくれます。
おもちゃと一緒に未来を考える
今回は、子供にあった最適なおもちゃについて紹介しました。
おもちゃは子供が小さい時の話だけではありません。
大人になってからも形を変えて遊びつづけます。特に男の子は、それがゲームになり、趣味になり、人生になっていきます。私でもあなたでも変わらない事実です。
ダウン症の子にとって、おもちゃは遊び場でも教育の場でもなく、コミュニケーションツールの一つと考えてくださいね。
特徴を見極めてうまく子供に当てはめてやれば、嬉しい気付きも沢山出てくると思います。
子供に興味のないものや合っていないものを与えれば、コミュニケーションロスとなり親との関係もうまくいきません。
なので、おもちゃを通して子供と一体になる、楽しい未来を想像して、おもちゃ選びを一緒にしましょうね!
