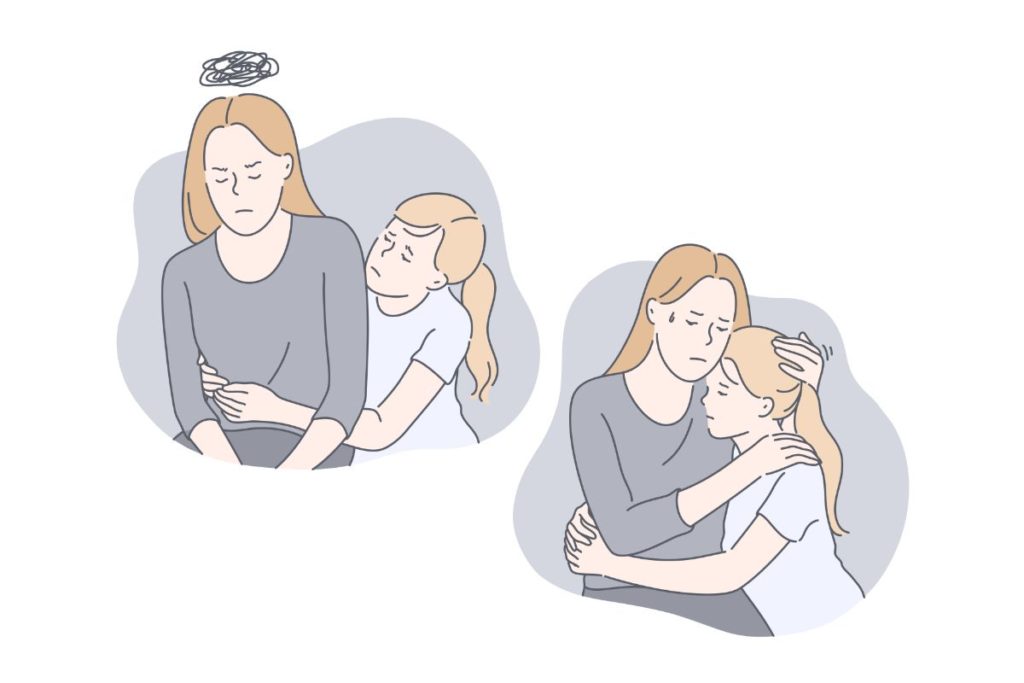
ダウン症の育児には大変なことも多いと思います。自分はダウン症では無いのだから、親族などにダウン症がいない限り、それは未知の世界ですよね。ほとんどの人が障害者の子育てなど知らないことばかりなので、マイナス面ばかり見たり、ネガティブな感情と紐付くことも多いです。
知らないことばかりなので、良くしようと思えば思うほど上手くいきません。
逆に、知らないことがすぐに上手くいったり、改善したら苦労はないでしょう。なので、特徴のある子の育児の始めは不安が大きいです。
しかし、親は、少し子供の年齢が少しづつ上がり、出来ることが増えると前向な考え方が出来るようになります。子供のを信じるのではなく自分を信じてください。
前向きな行動が少しでるのかというと、ダウン症の子供の良い未来を、すこしづつ確信し始めているからです。
今回は、ダウン症の育児で大変なことはあるけど、確実にそれが良い未来に繋がっているということをお伝えしますね。
育児で大変なこと3つ
育児は子供中心ですが、親自身の生活も大変です。とくにママは体力と気力の限界をさまよいならが育児をしていると思います。
パパがサラリーマンや公務員だと、家事育児の負担が大きくなる傾向があるし、どうしても自分の生活のルーティンを崩したくないので、子供の予想外だったり常識外の行動があると、怒ったりイライラしがちです。
なので、育児をうまく続けていくためには、
- お金を稼ぐための「仕事」
- 自立するための「教育」
- 健康な心を保つための「体の成長」
が必要になります。
お金を稼ぐための「仕事」
1つ目の大変なことは、子供を育てていくために、多かれ少なかれお金を稼ぐ必要があります。それはパパの仕事だったり、特別児童扶養手当などの支給金があります。
ママの場合、仕事が好きだったり、家計のために続けて行く必要がある場合でも、仕事を制限しないといけないような選択をせまられることもあります。たとえば、子供に疾患があったりすると、月4回程度は平日に通院しないといけないでしょう。すると、フルタイムの仕事は難しくなっていきますよね。
仕事の量が減ると、会社での役割が減ったりしてモチベーションが無くなったりしてデメリットが大きいです。また貰えるお金が減るので生活水準が下がります。
仕事を辞めるとなると、家事育児の専業主婦になりますが、それでストレスが貯まることも多いでしょう。
なのえ、そのような状況であれば、一度これまでの常識を変えてみるのが良いです。たとえば、育児を誰かに任せることや、自分でお金を稼ぐことを真剣に考えてみるのです。
マインドを変えてみて、状況に対応した新しい方法を考えてみるのも生活を保つ為に必要なことです。
子供を預けようと思えば支援サービスがありますし、お金は自分でネットひとつで稼ぐ方法が色々ありますよ。あなたにとって本当に必要な情報に気づかないのは理由があります。
自立するための「教育、学校」
2つ目は、あながた子供が自立するために、どのような教育が正しいのかと悩むことです。
学校教育では、小学校の普通学級や特別支援学級、ろう学校、児童デイサービス、療育センターなど多岐にわたりますよね。
ダウン症の子は、特別支援学級や、普通学級などの選択肢もありますが、どちらでもよいと思います。なぜなら、社会性が育つからです。ダウン症は自発的な行動や思考が弱いので、支援してくれる仲間や、同じレベルの子と関わっておくのがいいです。
親以外からの働きかけが本人にとって生きやすい世界に繋がります。個人的には、本人よりも少し上の年齢の目線での遊びや行動が良いと思います。もちろん先生の判断もあると思いますが、選択肢を減らす理由はありません。
もちろん特別支援学級へ行ったとしても、個人差があり、本人に本当に最適な教育が出来るかは分かりません。また、理科など普通学級と合同に実施する場合もあるそうです。
子供にたくさん働きかけて刺激がある時間が多ければ多い程よいし、自立を進めるためには、本当に子供本人が好きなことを、社会性の中から見つけてくることが大事になります。
それは子供が話してくれることもあるし、よく見て親が気づいてあげる視点が必要です。
健康な心を保つための「体の成長」
3つ目の大変なことは、体の健康的な成長です。
ダウン症の子供の多くは生まれながらにして疾患がある子が多いです。健康であっても知的障害がある場合がほとんどです。成長速度は健常者の半分程度といわれていますが、個人的にはもっと遅いと感じています。
次男は6歳でIQ20後半だったので、健常者の半分もいっていませんでした。
他にも、発声や話し言葉の療育させることはみなさんが考えていると思います。近くのST(言語聴覚療法)の先生に見てもらう方法が有効ですが、通うのが大変だったりしますよね。
またすぐに成果が出るわけではないので、続かなかったりします。
私は、長続きしなかったのは、STが高齢者向けに作られた制度であることで、あまり障害を持った子供に向いていないかなと感じたからです。
ダウン症の子供は、舌が大きいのも特徴で、発声に影響しています。また歯並びや虫歯にも繋がることがあります。鼻炎になることも多く、そうなると匂いや味が分かりづらかったりして、記憶に必要な五感が鈍ってしまうかもしれません。
どんな体の成長でもそうですが、障害者の療育には時間がかかると言うことです。
時間がかかると、成長に変化がみられなくて、焦るかもしれません。
子供は一生懸命成長していますが、親だけが焦っていないでしょうか。たとえば、パパは子供とお酒を酌み交わしたいなどの願望があったりしますよね、男の子であれば特にその思いが強いかもしれません。
そうした理想の未来が確信できるから今育児も頑張れるわけです。それが難しいと思ってしまうと、何故かパパは育児に興味が湧いてこないのです。
そうした場合、体の成長も、家族の心の成長を同じだと考えてみましょう。
体にも心にも一番いいのは、理想の未来を想像しながら生活することです。お酒を酌み交わす以外の理想を見つける必要があります。
それが見えてくれば、不安な状態からプラスのエネルギーがはたらき、勝手に未来が変わっていきます。
親の心の健康が1番大事
前にも書いた通り、ダウン症の子供の成長はゆっくりですよね。特に男子は、ほんとに半分以下だと感じます。なので、親はその分、自分の成長スピードを上げることが重要です。
どういうことかと言うと、親も現状維持思考で今日をなんとか乗り切ろうとばかり考えていると、うまくいかない過去のばかり思って後悔したり、前進することが出来ません。
なので、親のマインドを変えて成長しましょう。
目標ややりたいことをすでに出来ている親は、過去ではなく未来を見ている傾向が強いです。ただ漠然と想像するのではなく、どのように感じて家族がどうしているのか、具体的にどんな未来を作ればいいのか、すでに知っているからですね。
子供と一緒に未来を見る
現状が変わらないのは、あなたのマインドが長いこと変化が無いからです。
忙しかったり、やりたいことを出来ていないとか思っていたり、子供の成長や教育でどうしていいか迷っている時は、他の方法が見えていません。
現状を作っているのは過去の記憶です。今日の悩みは、あなたが普段接している情報や周りの人から影響をうけたもので出来ています。
例えば、会社の上司やママ友などで、イヤなことや、高圧的な態度を取られてが悩んだことがありませんか?理不尽なことがあると、その考えが頭をグルグル回り、うつっぽくなることもあるでしょう。
あなたの常識で考えているので、どうしたら解決するか答えが出ずに永遠にグルグルと考えます。
そのような時は、理想の本当になりたい状態を考えてイメージしてみてください。
イヤでどうしても関わりたく無いのであれば、関わりを断つことができる未来をイメージしてみましょう。すると、どうすれば関係を無くせるのか、自分のリラックス出来る環境はどうやったら作れるのか分かります。
それを強くイメージできれば、心も落ち着いてくるし、未来を実現しようとプラスな気持ちで行動的になれます。
そして、自分を変えるには、未来を当たり前にして思考したり、今まで出会ったことのないジャンルの人と繋がって、別の考え方を手に入れることが最短ルートです。
今回は、ダウン症の育児で大変なことから未来を見る方法について話しました。
あなたの生活をうまく続けていくためには、お金を稼ぐための「仕事」、自立するための「教育」、健康な心を保つための「体の成長」が必要でした。
メディアやこれまでの常識に捕らわれず、自分がこうなりたいという未来を強く想像してみましょう。そしてダウン症の子の成長は時間がかかることを受け入れると、自然と新しい生活スタイルが思いつくでしょう。
そのために、まず自分のマインドを変えてみてくださいね。
↓↓↓ おすすめの記事 ↓↓↓
子供の可愛さ3倍!セルフコーチングを上手に実践!
